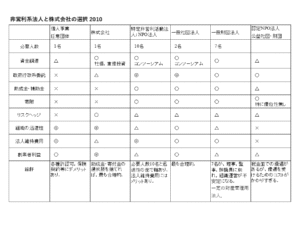先日,地域貢献型の事業をたちあげる・たちあげたい・経営している方むけのセミナーで話す機会があった.
2005年ごろの兵庫県では,毎週のように,どこかで同じような講座があったけど,いわれてみるとここ10年くらいは,殆どみかけなくなった.
「そもそも・・・」な質問を受けたので,起業するときの法人選択と一緒に,資料をまとめてみた.
NPOのそもそも
「社会課題には無償対応,社会貢献資金は自力で儲ける」
がNPOの大原則.
法人税法上の非課税を選択している時点で,NPOではない
ビジネスで儲けて,社会課題へ還元するという意思がないフェイクNPOである.
CSRの方が,レベルが高い.
ただし,社会福祉関連の政府市場(高齢者福祉,介護,障がい者福祉,保育,教育ほか)で事業展開している場合は,別世界になる.
それゆえ,特定非営利活動法人(NPO法人)などの非営利系組織は,
「利益率が高いビジネスを実現し,社会貢献・社会課題対応に必要な資金を儲けなければならない」
NPOって,儲けてはダメで,ボランティアなんでしょ,という誤解通念は,
25年以上前から,誤解されたまま.
継続寄附を主な収入源として事業を組む勘違い
時代にあわないし,そもそも日本にあわない.
寄附には世界標準として10%ルールがある.
寄附金のうち10%は組織の運営費として使用できるが,残りの90%は社会課題の現場に届けて当然というもの.
例えば,日本のクラウドファンディングは,プラットフォーム運営者に20~25%ピンハネされ,
支援先の組織の日常運営費に20%がきえるとすると,
社会課題の現場には60%以下しか届かない.
端的に寄附金中抜きビジネスである.
世界標準からは,ビジネスモデルの段階で,破綻している.
寄附を受けるには,「相応の代表者たちの能力」と「極めて明確な社会課題」の両方が揃っている必要がある.
1000-100-10人材の要件は必須条件である.
西日本で5人くらいしかいない.
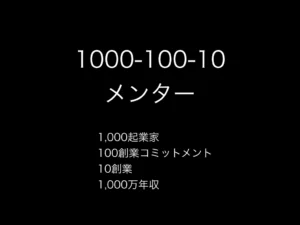
「社会課題には無償対応,社会貢献資金は自力で儲ける」
「継続寄附を主な収入源として事業を組む勘違い」
をあわせて,合理的に解釈すると,
寄附に値する能力十分なNPO経営者は,社会貢献資金を自力で儲ける選択をしている.
したがって,寄附を前提とするNPOは三下・三流以下と解釈できる.
つまり,そもそも寄附に値しないレベル.
行政の下請け業者になりたい
日本では,行政の下請け業者になって既得権を獲得することが,NPOの目標・目的になっている人たちが多い.
最初からそうなのか,事業を継続していくなかで選択肢がなかったのか.
NPO発祥の地ともいえる兵庫県では,当初,協働相手・パートナーシップという建前のなかで,NPO基盤整備がはじまった.
しかしながら,指定管理者制度の導入で,NPOの一定数が,指定管理の毒に侵された.
その後,就業困難者・若年失業者・ひきこもり支援の下請けが流行った.
この毒は,なかなかの猛毒.
さらに,駐輪場管理や公園管理などの下請け業務にも進出.
もう闇魔術級の毒.アニメの世界でしか解毒できない.
人類社会の当たり前のことで,
MLBの選手になりたい人は,ソフトボールチームで練習することはないし,
ソフトボールチームのコーチがMLB選手のコーチをできると言っても,だれも信じない.
同じ理屈で,
年収300万円未満のNPOスタッフが,将来の再就職を支援しますと自己主張したところで,
300万円未満の仕事しかみつけることはできないし,常識的に考えれば,本気で再就職したい人はNPOには相談しない.
※Indeed求人情報ベース
NPO法人職員
月給 17万円~23万円程度(年収換算で約204万~276万円程度)
人類社会に,トンビが鷹を育てる,という奇跡は,奇跡の確率(1/10000くらい)でしか存在しない.
さらに状況が深刻なのは,Social Startupの相談を,その辺のNPOにしてしまう人たちだ.
起業するときに,300万円しか稼げない人(それも行政の下請け業務での300万円だから実際には50万円くらいの能力しかない人)に,起業の相談をすることが,どれだけおバカなことか理解できないみたいだ.
その時点で起業家の資質が無い.
ボランティア団体を立ち上げたい,とか,行政の下請けをしたい場合は別.
同じ理屈で,商工会とか商工会議所に相談にいく人も,なかなかキビシイ.
シードマネーを探しに行くとか,商談相手の紹介依頼などが目的ならまだ合理的だが,
起業のビジネスプランを相談して,かつ,商工会議所スタッフのアドバイスを真に受けてしまう人は,
起業はあきらめたほうがよい.
公的機関のサラリーマンのアドバイスなんて,99.8%的外れだ.
理由は単純,起業したことも経営したこともない人たちだからだ.
社会貢献
社会貢献や社会課題に取り組みたい場合,経費処理の選択肢が増える点で法人の方が有利だけど,
法人格によって実現可能な社会貢献に差はない.
国境なき医師団を株式会社で事業展開できるか?
答えはできる.
F1パイロットのようなスポンサーロゴを全身に貼り付けたユニフォームで作業すればよい.国境なき医師団でできるなら,すべてのNPOの事業を株式会社でも実施できる.
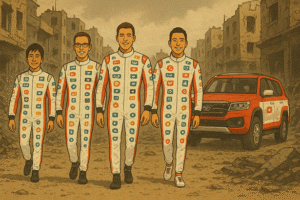
以上,Social Startup創業時の法人選択をまとめてみた.
寄附金を受け取る選択肢を残したいのなら,一般社団法人
寄附金不要なら株式会社の方が合理的.
行政の下請け目指すなら,認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)の方向でもよいが,発想としては平成の負の遺産である.
上記の通り,NPOの基本を無視した存在だから.
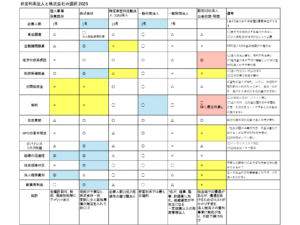
参考までに2010年ごろの法人選択資料を掲載する.
社会として非営利系法人に期待がのこっていた時代,と言えるかもしれない.