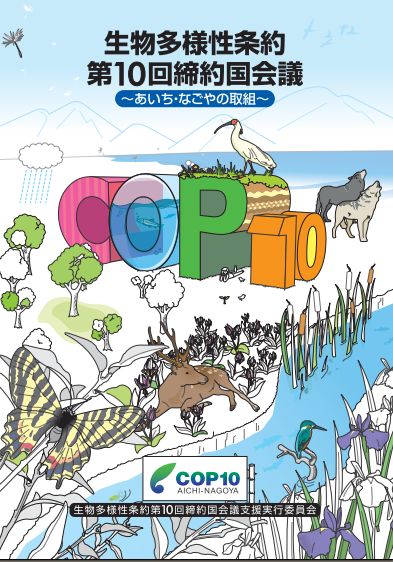(%エンピツ%)(%エンピツ%)「いのち」と「暮らし」を支える生物多様性を私たちは、自らの手で危機的な状況に陥らせています。
すべてのかけがえのないいのちを守り、その恵みを受け続けていけるように、今、行動することが必要なのです。
◇生物多様性の3要素
●種の多様性
文字通り、いろいろな生きものがいるということ。
気候や土地の状況など、さまざまな環境に応じて、多様な生きものが生まれた。
●生態系の多様性
森林、里山、河川、湿原、サンゴ礁など、生きものがくらす環境のこと。
さまざまな生態系があることが、種の多様性のもととなる。
●遺伝子の多様性
同じ種の中でも、遺伝子のちがいによって個体の差があること。
姿や行動がちがったり、性質に差があったり、さまざまな個性がある。
◇生物の多様性がもたらす「めぐみ」
◇環境省が定めた「生物多様性」を説明するためのコピー。
「地球のいのち、つないでいこう」
◇名古屋で2010年10月に生物多様性条約会議 多様な生きものをその環境とともに守ることなどを目的に、1992年に生物多様性条約ができた。
191の国と地域が加盟している。2010年10月、愛知県名古屋市で同条約の第10回締約国会議(COP10)が開催される(18〜29日)。
02年にオランダで開かれた第6回会議で、10年までに生物多様性が失われる速度を大幅に落とすことを申し合わせたが、成果があがったとはいえない状況だ。
名古屋の会議では、この間の取り組みの検証とともに、今後の活動の目標などが話し合われる。
詳細は>>http://mainichi.jp/select/wadai/wakaru/kankyo/archive/news/2010/20100104org00m040038000c.html
◆環境省
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/index.html#top
◆リーフレット
http://cop10.jp/aichi-nagoya/biodiversity/pdf/cop10-pamphlet02.pdf