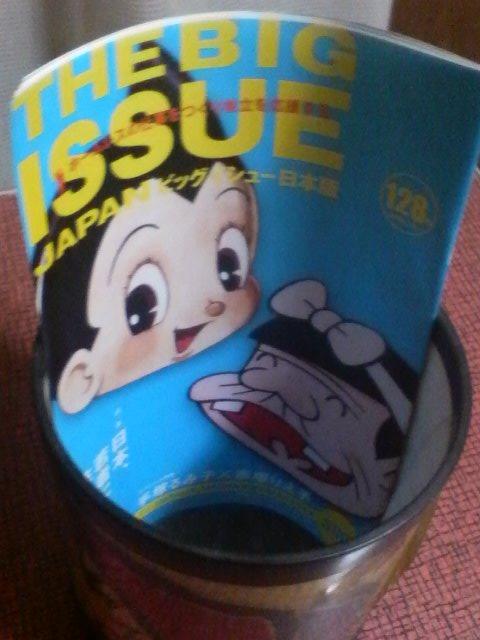10月28日に佐野章二さんの講演に行ってきました。
今回、佐野さんは大阪ボランティア協会主催の関西NPO支援センターネットワーク(knn)第十三回研究会のゲストとして来られました。
佐野章二さんはビッグイシューの代表で、現在はホームレスの支援を精力的に行っておられますが、講演では主にこれまで関わってこられた多くの活動について話されました。
佐野さんはホームレスを支援するためにビッグイシューを立ち上げたわけですが、皆がやっていない支援を考えたそうです。現在ホームレスの人々に自助、自立を促すために、路上で雑誌を販売してもらい、その売り上げの五十パーセント以上を彼らの収入にするという活動を行っています。
ビッグイシューには六つのコンセプトがあり、一つ目はホームレスに仕事を与え、明日につなげる。二つ目はものや金でなくチャンスを与える。三つ目は問題の当事者が解決の担い手になる。四つ目はビジネスの手法でもって社会にチャレンジする。これはビッグイシューがNPO法人ではなく、有限会社であるということと深く関わりがあります。五つ目はホームレスをビジネスのパートナーとする。六つ目は会社と平行してNPOを作る。
佐野さんがこのビッグイシューの構想を練り、他の人に話したところ、百パーセント失敗する、無謀だからやめておけと忠告されたそうです。
その理由としては①若者の活字離れが進んでいるので、主に若者を対象にした雑誌を販売するのは難しい、②イギリス等とは違い日本には路上で売り買いする文化が根付いていない、③インターネット等の普及により、情報はタダの時代という認識が広まっている、④売り手が可愛い姉ちゃんならまだしもホームレスでは誰も買わないだろう、といったものでした。
この緒問題に対し、佐野さんは一つ一つ答えていきます。
①に対して、近頃の若者は携帯等でよくメールを送って活字を使っている。②に対しては、もし大型書店で売れば埋もれてしまう。路上の人がよく通る場所の方が条件が良い。③に対しては、ビッグイシューは普段記者が書きたくても書けないことが載っており価値がある。そして④に対してはホームレスは足腰が強いので、路上で物を売るのに適している。
記者会見では内容もさることながら、やる気が伝わるととりあげるそうです。またテレビの方もホームレスをとりあげたいが、カメラで顔を写すのは難しい。だからビッグイシューを通してホームレスを報道出来る状況もマスコミがこの活動を大々的にとりあけた要因の一つだろう、と語られていました。
非常に精力的に活動されている佐野さんですが、最後の質疑応答でその活動の原動力はと尋ねられ、やりたいことをやることと自分の考えや思いにこだわることだ、と言われたのが大変印象に残りました。自分も同じ様な考えをもっており、自分にそれを言い聞かせ今まで奮い立たせてきたので、とてもその言葉には共感できました。己のやるべきこと、やりたいことを実践し、身を以て世の中にその重要性を伝えていければと思います。
また活動の中でお会いできることを楽しみにしています。
この佐野さんの講演についていつもお世話になっている市民事務局かわにしのブログでも紹介しています。ぜひまたご覧ください。エッグマンの簡単な自己紹介(〃∇〃) もあります。
ボランタリーライフ.jp版: 佐野さんについての記事。自己紹介。