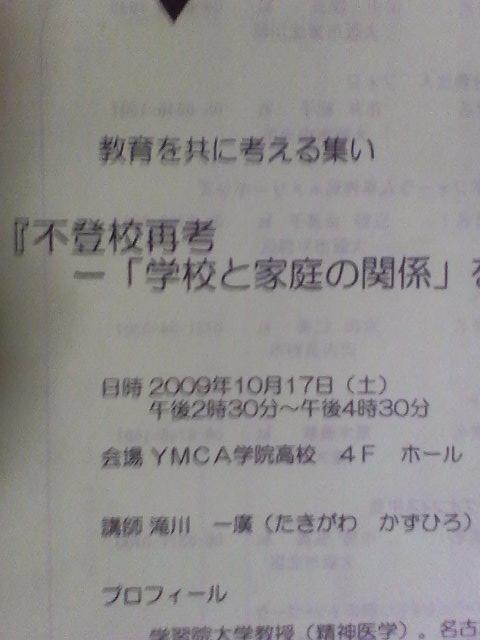学校に行く意義と言いますと何か哲学的な話になりそうですが、それは後のお楽しみにしておいて、まずは経済学的に、意義というよりも実際「なぜ学校に行くことが合理的であるのか」、或いは「なぜ合理的であると感じられる状況が生まれるのか」について考察します。
まず昭和22年に新しい教育基本法が施行された当初の子供の学校への長期欠席理由のトップ3は病気、経済的理由、親の不理解でした。この親の不理解とは学校側からの物言いであり、親からすれば食うにも困っているのに大事な働き手を長い間学校に預けることは「合理的」な判断とは思えなかったでしょう。
ではいつから学校に行くことが親たちにとって、或いは世間的に「合理的」なものになったのでしょうか。
六十年代、勉強すれば進学でき、それにより幸せをつかむことが出来るという世間の共通認識ができ、進学率が急速に上がり、それと比例するように長期欠席率が下がりました。このことから恐らくこの頃には学校に行くことは合理的であるという認識が世間一般に広がっていった、と考えられます。
ただ新しい概念(この場合、学校に行くことが良いことだ、得である)が古い概念(この場合、学校に行く必要なんかない、働き手を失って損である)にとって変わるには、それなりの理由が必要です。様々な理由が重なり関連しあったと考えられますが、大きな理由の一つとして考えられるのは経済復興でしょう。
経済復興が進み家計に余裕が出てきて、子供を学校にやれるようになったのが、まず一点。そして後にも個別に分析しますが、経済が発展し、工業化が進むにつれ農業や林業等の第一次産業からものづくりの第二次産業やサービス業の第三次産業に経済がシフトし、学校卒業者の就職口が急激に増えていったことが第二点。さらに豊かになるにつれ、医療状況や食料状況も改善され、三大長期欠席理由の一つ、病気(主に身体的な)による不登校が少なくなったことが第三点。
これらの理由が重なり学校に行く子供が増え、それが当たり前となり恒常化し、先程述べた「学校に行けば幸せになれる」という“神話”が生まれます。正にパラダイムの変化です。
経済や社会の変化は人々の認識や思考パターン、時には信念にさえも影響を与え、それをマスコミ等のメディアがさらに喧伝し、変容を強化していくという図式は今にも通じるものがありそうです。
しかしその後この“学校神話”にはその絶頂を迎えた瞬間に崩壊の兆しが現われます。