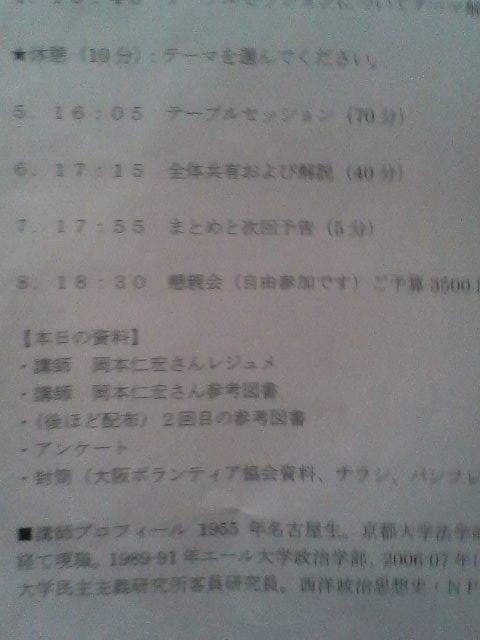さて後半はいくつかのテーマに分けて、小グループごとにテーブルに別れ話し合いました。
テーマの中では「民主主義と愛国心」というのにも非常に興味をもち、激しく論じてみたいと思いましたが、やはり初回は自分にとってベタな「教育と市民自治」から始めてみようと思い、テーブルにつきました。
他のメンバーの方は教育関係やその他の市民活動や仕事をされていて、それらの体験等から様々なお話を聞かして頂きました。私も体験等を交えて、皆と市民教育はどうあるべきか論じました。
そしてそのセッションの時間の後に各グループから代表を選び、プレゼンテーションをしました。最初私たちのグループからは誰も名乗りあげなかったので、何故か一番年の若い人が出るということとなり、私が(他にもっと若い人が潜んでいたかもしれませんが)手を挙げることになりました。
私は実は笑いの勉強をしていたことがあり、舞台に出た経験もあるので、そのこともあって真面目にメッセージを伝えるのは当然だが、前にでて発表する限りは笑いをとらねばならない、と自分に変なプレッシャーをかけ、緊張の面持ちのまま発表に臨みました。