宮城県美術館講堂で、「アクセスアーツフォーラム〜障害のある人の芸術活動を通した社会参加」と題した事例報告とパネルディスカッションがありました。
事例報告を行ったのは、「たんぽぽの家アートセンターHANA」の柴崎由美子さんとアーティストの山野将志さん、「アートプラネッツ・みやぎ」・「美楽アートクラブ」の小島まことさん、「ミューズの夢」の島崎詠子さん、「みやぎダンス」の定行俊彰さんの4組。

美術、音楽、パフォーマンスといったジャンルで障害者とともに歩む団体の事例報告は、実に実り多いもので、しかも当然ながらたいへんリアルなものでした。
それぞれから共通して聞こえてきたのは、アートが人と人を結ぶもの、ということで、障害のある人に焦点があたってはいるものの、障害のある/なしにかかわらず、それはいえることなのだろうと思います。
逆に言えば、あまりに表面的な必要性によってのみ人と人との関係性がとらえられる中で、そうではないある意味純粋におもしろいとか、感動できるという意味で人と人とが関係性を構築できないのはおかしいのではないか、という疑問の中から、こうした障害のある人の社会参加とか、あるいは障害のない人の日常生活、例えば商店街を使ったアート・プロジェクトという発想が生まれてくるのではないかと思いました。
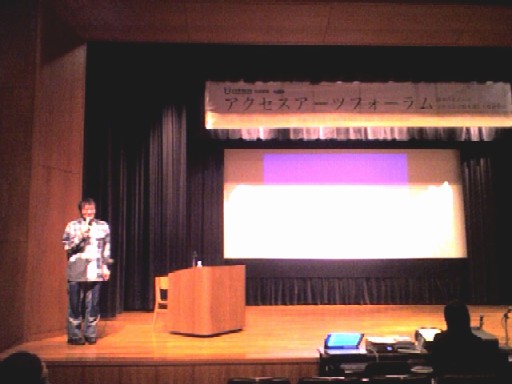
事例報告の後のパネルディスカッションでは、来場者の質問などをもとに意見交換が行われましたが、おもしろかったのは「アートの質」に関する議論で、この場合、われわれが議論している「質」というのは技術的な質のことではなく、表現の質のことではないか、という宮城県美術館の齋正弘さんの指摘はとても的を得たものでした。
そうした意味でも「こんなもんだ」的な妥協、一見、伝わっていないようだから「意味がない」という的な偏見には決して屈したくないという小島まことさんの強い信念には共感をおぼえました。
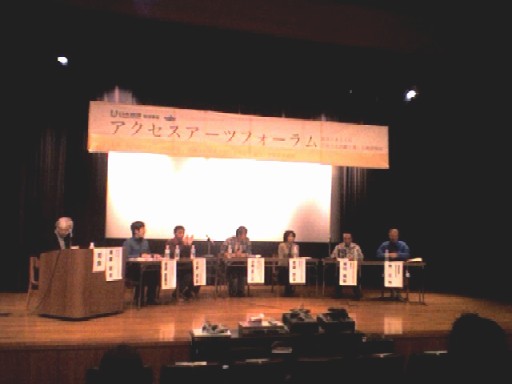
また、福祉の現場ではその人の力を高めて行く作業をいかに手伝っていくかが現在問われている、という柴崎さんの話は、アートそのものについても言えるように思います。
アート作品はそれだけで意味があるといった考え方もありますが、アートはよりよく生きるための技術(アート)なのだと思います。それははしごのようなもので、上の階へのぼってしまえば、捨て去られてもかまわないものなのではないかと思います。抜け殻のようなそれを大切に保管・保存したりするのは、もうアートの仕事ではないのではないか、そんな風に思えます。
(コメント:門脇篤)
